現状、クイズ界には統一的な公的組織がありません。そのため、ほとんどの大会では結果を残したとしても学校で表彰されることはなく、公的な組織がないこともあり、学校内での信用も得にくく、部として認められにくい、実力に対して周りからの評価を得にくい、学校内で立場が向上しない、予算がつかない、など様々な問題があります。
また東大王など全国放送のクイズ番組も終了していき、クイズブームがいったん落ち着いたことで、今後のクイ研運営はより難しくなっていくことが予想されます。
このような状況の1つの解決策として考えられるのが、公的な統一組織の創設もしくは高文連のクイズ部門の創設です。全国高文連は公益社団法人で、「全国高等学校総合文化祭(全国高総文祭)」等の事業や研修会の実施などを通して、高校生の部活動を支援する組織で、47都道府県高文連と19全国専門部(演劇、合唱、吹奏楽等)を正会員としています。
現在の学生主体のクイズ大会の運営文化を残しつつも、公的な大会の開催を実現していくことで、各校のクイ研の地位の向上や、部への昇格・部の存続をしやすくなります。また公的な統一組織も創設しやすくなり、クイ研の立ち上げ時に問題となる早押し機の貸出しなど、クイ研部員が活動しやすくなる環境づくりが進められていく可能性が高まります。
この全国高文連にクイズ部門を創設するためには、まず各都道府県の過半数、つまり24の都道府県の高文連にクイズ部門が創設される必要があります。各都道府県の高文連へのクイズ部門の設立の条件は異なるため、ここでは最もクイ研の数が多いと考えられる東京都の条件を見ていきます。
まず高文連に加盟している学校の中で5、6名程度の教員(顧問でなくても可)が理事となり、代表者を決める必要があります。東京都教育委員会の組織のため、都立学校の先生が入っているとスムーズに進んでいきます。
その後、現在のクイズ界の現状や、加盟することでどのように生徒たちの役に立つかなどを明確にし、規約を作成します。その文書を送り、加盟の申請を行います(高文連の担当の方との打ち合わせなども必要です)。その後大会の視察などを得て、高文連の理事会で承認されれば、クイズ部門が設立されることになります。直近では2024年にボードゲーム部門が創設されました。
クイズ部門が創設されると、11月前半に高文連の文化祭で大会の実施なども可能になります。文化祭は東京都教育委員会と東京都高文連の共催で、費用の大部分を東京都教育委員会の負担で行われます。公欠が認められる可能性もあり、大会で優秀な成績を収めれば、学校で表彰される可能性が高まります。
まず生徒側が出来ることとしては、教員側に高文連の加盟について説明したうえで、メンバー入りをお願いすることが考えられます。都立学校の教員が入っていることが絶対条件です。5、6名の協力して頂ける先生方が集まった場合には、教員側が加盟への手続きを進めていくことになります。
現状5校以上のクイ研が存在すると考えられるのは、北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、愛知、長野、静岡、奈良、大阪、兵庫、三重、福岡など24には及びませんが、東京都よりも教員の先生方の人数が少なくても良い道府県の方が多い可能性がありますので、検討してみてください。クイズ部のある高校が団結して、自県の高文連に対して専門部設立を求めていくところがスタートとなります。
もし24以上の都道府県でクイズ部門が設立された場合には、全国高文連へクイズ部門が創設できる可能性が出てきます。以下が規定になります。
全国高文連入会及び退会規程より抜粋
(全国専門部の要件)
第5条 (中略)高等学校文化連盟全国専門部(以下、全国専門部)は次の要件を満たすものとする。
(1) 原則として各都道府県高等学校文化連盟の過半数に登録されている専門部の全国組織であること。
(2) 既に承認されている全国専門部と活動内容が同じ又は酷似していないこと。
(3) 全国組織としての体裁を整えていると認められること。
ア 規約等が整備されていること。
イ 役員(部会長、理事長、事務局長等)が選任されていること。
ウ 事務局が設置されていること。
エ 具体的事業内容が明確になっていること。
オ 経費の調達方法が確立しており、使途が明確であること。
カ その他全国組織として継続が可能であると認められること。
全国高文連へクイズ部門が創設された場合、全国高総文祭において、各部門が定めた選考方法により各都道府県において代表生徒を選考し、公的な全国大会開催の道が開けます。この大会自体は、教員により運営は難しいと考えられるので、現状、比較して学校としても認めやすいシステムを取っている大会(例えばAQLさん)あたりを公的な大会にしていくことで、会場負担など運営面での負担が減り、双方にメリットが大きいと考えられます。またその他の大会を実現していく道も開けます。

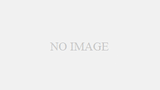
コメント